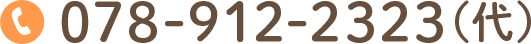![]()
身体的拘束最小化のための指針
身体的拘束最小化のための指針
はじめに
身体的拘束は患者さんの権利である自由を制限する、極めて非倫理的な行為です。明石市立市民病院(以下、当院)は患者さんの基本的人権を尊重できるよう、身体的拘束の最小化および適正化に向けて以下の指針を定めます。
1.身体的拘束の最小化に関する当院の基本的な考え方
当院では、緊急やむを得ない場合を除いて原則身体的拘束を行いません。
身体的拘束を正当化することなく、職員一人一人が拘束による身体的・精神的弊害を理解し、可能な限り身体的拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2.身体的拘束とは
(1)定義
入院療養上の安全を目的に、安全帯等、身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に身体を拘束し、その運動を抑制する等により行動制限をおこなうこと。
(2)使用用具およびその目的
| 安全帯(体幹) | ベッドから自分で降りられないようにする。 |
|---|---|
| 安全帯(手首・足首) | 手足の機能を抑制し点滴・チューブ類の自己抜去や他者への迷惑行為を防止する。 |
| ミトン | 手指の機能を抑制し点滴・チューブ類の自己抜去や危険行動を防止する。 |
| 車椅子用安全ベルト | 車椅子から立ち上がれないようにする。 |
| 介護服(つなぎ服) | 脱衣やおむつ外し、点滴・チューブ類の自己抜去を防止する。 |
| 転倒むし(クリップセンサー) | 衣服につけて動きを把握する。 |
| 4点柵(壁付け含む) | 四方を囲みベッドから降りられないようにする。 |
3.身体的拘束を行う緊急やむを得ない状況とは
患者さん本人または他者の生命または身体を保護するための措置として、以下の3要件をすべて満たす状態にある場合は、
医療者複数で協議し、患者さんやご家族等への説明・同意を得た上で、必要最小限の身体的拘束を行います。
| 切迫性 | 患者さん本人または他の患者さんの生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
|---|---|
| 非代替性 | 身体的拘束を行う以外に代替する医療・看護の方法がないこと |
| 一時性 | 身体的拘束が必要最低限の期間であること |
4.身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為について
当院では患者さんの行動パターンにあわせた、身体に触れないセンサー類やモニター類を適宜用いることにより、転倒転落事故の防止対策として行う身体的拘束の最小化を目指します。
5.鎮静を目的とした薬物の適正使用について
薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しませんが、薬剤による鎮静を必要とする治療や検査においては、鎮静薬の必要性と効果を評価し、
過度の鎮静がかからないよう注視しながら適正量の薬剤を使用します。また、行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、薬物を用いない対応を優先し、薬物の使用は必要最低限にとどめます。
6.身体的拘束最小化のための体制
身体的拘束最小化に向けた取り組みを継続的に実施し、体制を維持・強化します。
(1)身体的拘束最小化チームの設置
身体的拘束最小化チームを設置し、やむを得ない状況で身体的拘束を実施する場合でも最小限に実施する体制と早期の解除に向けた取り組みを整備することを目的としています。
(2)チーム構成
チームメンバーは病院長が指名する
医療安全管理室医師/看護師/薬剤師/理学療法士/医事課事務員/医療安全管理室事務員(事務局)/その他病院長の認めた者で構成します。
医療安全管理室医師/看護師/薬剤師/理学療法士/医事課事務員/医療安全管理室事務員(事務局)/その他病院長の認めた者で構成します。
(3)チームの活動内容
- 身体的拘束の実施状況の把握
- 身体的拘束が安全かつ倫理的に実施されているかの審議
- 身体的拘束の実施状況の職員への定期的な周知、徹底
- 身体的拘束を最小化するための指針の作成、周知活用、および定期的な見直し
- 職員に対する身体的拘束に関する情報提供、教育
7.身体的拘束最小化に向けた職員教育
可能な限り身体的拘束をしない医療・看護の提供に向け、本指針ならびに身体的拘束の実施状況の職員への定期的な周知、徹底を行い、職員研修を年一回以上開催いたします。
8.この指針の閲覧について
当院の身体的拘束最小化のための指針は、全ての職員に周知し、患者さんやご家族等が当院ホームページ上で閲覧できるよう公開します。