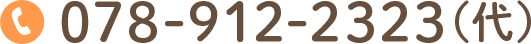![]()
 診療内容
診療内容 主な対象疾患
主な対象疾患 スタッフ紹介
スタッフ紹介
-
診療内容
明石市立市民病院の理念は、急性期病院・二次救急病院として安全で高度な医療を提供し、地域の医療機関と連携しながら、市民の皆さまの生命と健康を守ることです。
リハビリテーション科では、発症後、手術後の早期よりリハビリテーション(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)を実施し、急性期の身体機能・精神機能の回復を支援いたします。
2014年10月に地域包括ケア病棟、2019年2月に回復期リハビリテーション病棟を開設いたしました。急性期以降も継続してリハビリテーションが必要な患者さんには、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟にて引き続き入院していただき、円滑な在宅復帰・社会復帰を果たしていただけるよう支援いたします。
また、ご自宅に帰られる患者さんには、福祉用具の選定・住環境の改修・介護保険などのサービスの利用等について、提案や助言をさせていただきます。
施設基準
運動期リハビリテーション料Ⅰ
脳血管疾患リハビリテーション料Ⅰ
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ
廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ
がん患者リハビリテーション料 -
主な対象疾患
整形外科では、転倒後の、大腿骨頚部骨折や脊椎の骨折、上腕骨の骨折、前腕骨の骨折によって安静や手術が必要となる患者さんが増えています。下肢(股関節や膝関節)の変形性関節症や脊柱管狭窄症で手術を受けられる方も増えています。大腿骨頚部骨折や脊椎の骨折の手術後では、寝たきりにならない・させないために、早期からのリハビリテーション(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)の実施が重要となります。早期に座ったり歩いたりできるように、必要に応じて土曜日・日曜日も理学療法を行っています。また、医師が必要と判断した患者さんには手術前から理学療法を行っています。
上肢(上腕骨や前腕骨)の骨折の患者さんでは、片手が使えなくなることにより、日常生活がとても不便になります。早期より理学療法・作業療法を開始することで骨折部位の機能回復を進めるだけではなく、退院後にたちまち必要となる寝起き・食事・着替え・入浴・排泄といった日常生活動作の練習も、看護師と連携して実施しています。
脳神経外科では、脳梗塞・脳出血・硬膜下出血といった脳血管障害の患者さんが増えています。脳血管障害は手足の運動や感覚の障がい、言葉の障がい、食べ物を飲みこむことの障がい、認知機能の障がいを引き起こす病気です。脳神経外科での治療とあわせて、早期からリハビリテーション(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)を開始することが、身体機能や生活能力の回復のためには重要となります。医師の指示のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がより早期からリハビリテーションを実施いたします。
急性期以降も継続してリハビリテーションが必要な患者さんには、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟にてリハビリテーションを継続していただき、円滑な在宅復帰・社会復帰を目指していただきます。
循環器内科では、心筋梗塞や心不全などの患者さんに対して心臓リハビリテーションを実施しています。心臓リハビリテーションは、運動されている患者さんの心電図をモニターしながら、より安全に、適切な運動量・運動強度で実施しています。
カテーテル治療や投薬だけでは、心筋梗塞や心不全は再発しやすいといわれています。早期の身体機能の回復・社会復帰を目指していただくのはもちろんですが、心臓リハビリテーションを実施する目的としては、再発予防の観点が欠かせません。心臓リハビリテーションでは、退院後も心臓の機能を維持し、再発を予防していただけるよう、理学療法士による運動指導だけではなく、看護師による生活指導、管理栄養士による食事指導、薬剤師による服薬指導を包括して行っています。
外科の患者さんでは、胃や小腸、大腸、胆のう、すい臓のがんなどで手術された後のリハビリテーション(理学療法、作業療法など)を実施しています。手術後は創部(傷口)の痛みがありますが、早期の離床・歩行練習が傷の回復を早めて、日常生活能力の早期回復、早期退院、早期社会復帰につながるといわれています。できるだけ苦痛を軽減しながら離床していただくことから開始し、早期に社会復帰を果たしていただけるよう支援いたします。
糖尿病内科の患者さん、糖尿病で教育入院された患者さんには、運動療法の観点から、生活習慣の振り返りと見直しをお手伝いいたします。合併症の有無、生活習慣、就業環境、体力、運動の好き嫌い、様々な状況に合わせて生活活動量を増やし、血糖値をコンロトールするためのポイントやその方法を提案いたします。また、体組成計で全身の脂肪量や筋肉量を計測し、お体の状態に応じた運動プログラムを提案いたします。退院後も継続できるよう、入院中は理学療法士が一緒に運動療法を行っていきます。
その他の診療科の患者さんでは、痛みや発熱など体調の悪化によって体を動かすことが困難になったり、ベッド上での安静が必要となったりする場合があります。そういった場合には身体活動量が低下し、筋力の低下、体力の低下、関節可動域の低下、食べ物を飲みこむ力の低下、認知機能の低下をきたします(廃用症候群といいます)。早期に離床すること、ならびに歩行練習を開始することで廃用症候群を予防し改善することができます。リハビリテーション科では、あらゆる診療科の患者さんに対して廃用症候群の予防と改善のため、入院後、早期から理学療法・作業療法・言語聴覚療法を実施しています。 -
スタッフ紹介
スタッフ紹介
氏名 役職 専門分野 所属学会・資格など 黒田 司 部長 - 日本整形外科学会(整形外科専門医、運動器リハビリテーション医)
日本手外科学会(指導医、専門医)
日本リハビリテーション医学会(認定臨床医)医師のほか、リハビリテーション科では以下のスタッフが業務を行っています。
2024年5月現在、理学療法士25名、作業療法士9名、言語聴覚士2名、アシスタント2名です。
うち、専任1名、兼任2名の理学療法士が、併設する訪問看護ステーションでの訪問リハビリテーション業務に従事しています。
認定資格
名称 人数 がんのリハビリテーション研修会修了者 19名 3学会合同呼吸療法認定士 5名 日本糖尿病療養指導士 2名 兵庫県糖尿病療養指導士 1名 介護支援専門員 2名 認定理学療法士(管理・運営) 1名 認定理学療法士(脳卒中) 1名 認定理学療法士(代謝) 1名 認定訪問療法士 1名